知覚と記憶|第1研究室(写真・映像)

鈴木理策
Risaku Suzuki|教授|写真家
1963年和歌山県生まれ。東京綜合写真専門学校研究科修了。写真を中心とする作品を制作している。主な展覧会に「写真と絵画-セザンヌより柴田敏夫と鈴木理策」(2022年、アーティゾン美術館)、「意識の流れ」(2015-2016、丸亀市猪熊弦一郎現代美術館・東京オペラシティギャラリー・田辺市立美術館)、「熊野雪桜」(2007年、東京都写真美術館)など。第25回木村伊兵衛写真賞、第22回東川賞国内作家賞、2008年日本写真協会年度賞など受賞。
そこに現れる像は主観と客観が流動的に混じり合う。撮影者の意識を感じたり、記録として機能したりする様に。また、そこから想起される記憶は様々で、見る人によって経験の深さは異なります。写真や映像はうつしたものであり、うつってしまったものでもある。制作ではそこから考え始めてみるのが良いのではないでしょうか。
担当授業:IMA実技、IMA概論、写真表現演習I (前期)、写真表現演習I (後期)、写真表現演習II a、写真表現演習II b、写真映像論、写真史
知覚と記憶|第2研究室(映画・都市と建築)

石山友美
Tomomi Ishiyama|准教授|映画監督
1979年東京都生まれ。日本女子大学家政学部住居学科卒業。磯崎新アトリエ勤務を経て渡米。カリフォルニア大学バークレイ校大学院、ニューヨーク市立大学大学院で建築、芸術論、社会理論を学ぶ。ニューヨーク市立大学大学院都市デザイン学研究科修士課程修了。在米中に映画制作に興味を持つようになり、帰国後からインディーズ映画の制作に関わる。劇場公開監督作に『少女と夏の終わり』(2012)、『だれも知らない建築のはなし』(2015)。建築作品の記録映像をライフワークとして続けている。
「先端」というのは、なにかの「はざま」にあるように思います。例えば、慣れ親しんだ日常と未知なる風景との合間にといったような。そう考えれば、新たな表現のフロンティアは、実は私たちの生活のなかに息を潜めて存在しているはずです。慌ただしい通学時間に、友人たちとの他愛のない会話のなかに、バイト先の更衣室に・・・。対話を通して一緒に様々な「はざま」を探索できることを楽しみにしています。
担当授業:IMA実技、IMA概論、映像演習、プレゼンテーション論
言語と身体|第3研究室(作品コンセプト・グローバル社会とアート)

荒木夏実
Natsumi Araki|教授|キュレーター・評論家(現代美術)
パリ(フランス)生まれ。慶応義塾大学文学部卒業、英国レスター大学ミュージアム・スタディーズ修了。三鷹市芸術文化振興財団(1994-2002)、森美術館(2003-2018)のキュレーターを経て、2018年より現職。「ゴー・ビトゥイーンズ展:こどもを通して見る世界」(2014)で第26回倫雅美術奨励賞、第10回西洋美術振興財団学術賞受賞。現代美術と社会との関係に注目し、アートをわかりやすく紹介する活動を展開している。
他者を知ることによって自分を発見し、パーソナルな体験をパブリックな世界とつなげること。それを可能にするのがアートの力です。多様な素材や手法を用いながら、作り、考え、議論し、批評する。先端はこのように総合的な表現力を学ぶことのできる場です。アートを通して自分自身や社会に向き合ってほしいと願っています。
担当授業:IMA実技、IMA概論、現代芸術概論
言語と身体|第4研究室(社会彫刻・行為の芸術)

西尾美也
Yoshinari Nishio|准教授|美術家・ファッションデザイナー
1982年奈良県生まれ。東京藝術大学大学院美術研究科先端芸術表現領域博士後期課程修了。博士(美術)。文化庁芸術家在外研修員(ケニア共和国ナイロビ)、奈良県立大学准教授などを経て、2022年10月より現職。装いの行為とコミュニケーションの関係性に着目したプロジェクトを国内外で展開。ファッションブランド「NISHINARI YOSHIO」を手がける。
日常生活批判から「問い」が生まれる。それを深く勉強し、仮説を立て、調べ、実験や考察することが学問だが、先端ではその「やり方」に制限がない。技術や鑑識眼も前提ではない。問いを洗練させ、独自の方法で社会に投げかけること。何かをやってみることで世界を理解しようとすること。先端の門戸は、主体的、創造的に物事を探究しようとするすべての人に開かれている。
担当授業:IMA実技、IMA概論、芸術実践論文演習、拡張するファッション論、空間造形演習、色彩学
[web-site]
言語と身体|第5研究室(コミュニティとアート・臨床心理)

西原珉
Min Nishihara|准教授|キュレーター・心理療法士
90年代の現代美術シーンで活動後、渡米。ロサンゼルスでソーシャルワーカー兼臨床心理療法士として働く。心理療法を行うほか、シニア施設、DVシェルターなどでコミュニティを基盤とするアートプロジェクトを実施。2018年からは日本を拠点にアーティストや作り手のための相談と心理カウンセリングのほか、アートプロジェクトやセラピューティックな手法を通じたコミュニティのケアを探究。秋田公立美術大学教授を経て、2024年4月より現職。同時に秋田市文化創造館館長を務める。
波が砂に描く線のように、予測もコントロールもできない創造のプロセスは、不断に進化しています。それは飛躍や不連続を怖れず、失敗すら楽しみながら、つかまえようのないものをつかまえようとする、自由と情熱の波打ち際です。わたしたちはその波打ち際の「先端」で、描かれる線の先を追いながら、一瞬ごとに表現の限界を超えていきます。皆さんと共にそこに立つことを、心から楽しみにしています。
担当授業:IMA概論、IMA実技、現代芸術概論、芸術実践論文演習、複合表現演習
アートアンドサイエンス|第6研究室(実験音楽・メディア表現)

古川 聖
Kiyoshi Furukawa|教授|音楽家・作曲家
1959年東京都生まれ。高校卒業後渡独、ベルリン芸術大学、ハンブルク音楽演劇大学にてイサン・ユン、ジェルジ・リゲティのもとで作曲を学ぶ。スタンフォード大学で客員作曲家、ハンブルク音楽演劇大学で助手、講師、ドイツのカールスルーエのZKM でアーティスト研究員を歴任。理化学研究所など多くの学外組織と共同研究を継続的におこない、2018年には音とテクノロジーを核とする東京藝大発ベンチャーcoton社を起業している。
先端芸術表現科でいう所の領域横断性とはアートの枠内での移動や組み合わせではなく、アートとアートではないものの間を行き来しつつ、アートの外側の様々な場所に(たとえそれが困難な事であるにしろ)点を打ち続け、そのメタポジションから見えてくる、アート各領域の関係性を探るような、絶え間の無い動きのようなものだと思う。
担当授業:IMA実技、IMA概論、サウンド・アート概論
[web-site]
アートアンドサイエンス|第7研究室(メディアアート)
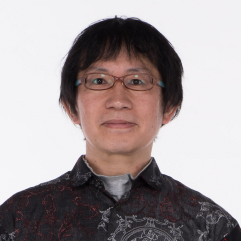
八谷和彦
Kazuhiko Hachiya|教授|メディアアーティスト
1966年佐賀県生まれ。九州芸術工科大学(現九州大学芸術工学部)画像設計学科卒業。卒業後、CIコンサルティング会社勤務と並行してアーティスト活動をはじめ、メールソフトPostPetを開発しSo-netからリリース。その後、自分達の会社PetWORKsを設立し、12年社長を勤めた後、2010年10月より現職。「メールを運ぶ」「人を乗せて飛ぶ」など、機能がある作品を作っている。
踊ってもいいし、音でもいいし、文章を書いても、写真でも映像でもいい。・・・・・・という風に「何を作ってもいい」と言われると、意外と人は悩んでしまうものかも。学生を見ると、たまにそういうことも感じます。けど、そういう風に真剣に悩む時間を人生の中で持つのは、実はとても大事で貴重、と思っているのです。
担当授業:IMA実技、IMA概論、複合表現演習3
アートアンドサイエンス|第8研究室(デジタル技術とサウンド表現)

牛 大悟
Daigo Ushi|准教授|美術家
1979年神奈川県生まれ。東京藝術大学大学院美術研究科先端芸術表現専攻修了。2004-2005、ドイツHFG Karlsruhe大学留学。2008年文化庁新進芸術家海外研修制度により中国滞在。2008-2011、北京電影学院新媒体芸術科研究員。 2011-2014、中国美術学院インターメディアアート科講師。 その後、先端芸術表現科助手、非常勤講師。芸術情報センター助教を経て現職。
現代美術と中国アートを軸に、デジタル技術とサウンド表現の可能性を研究しています。作品制作や教育、国際的なプロジェクトを通じて、多文化的な視点からアートの役割を探求してきました。特に、人工知能AIやVR仮想現実を活用した新しい表現方法には、大きな可能性を感じています。学生の皆さんには、対話を通じて創造性を引き出し、生涯にわたって探求し続けられる独自の表現を見つけてほしいと願っています。
担当授業:IMA実技、IMA概論、IMA演習
素材と創造性|第9研究室(絵画・インスタレーション)

小沢 剛
Tsuyoshi Ozawa|教授|美術家
1965年東京都生まれ。東京藝術大学大学院美術研究科壁画専攻修了。代表作に、地蔵建立、なすび画廊、相談芸術、醤油画資料館、ベジタブル・ウェポン、「帰って来た」シリーズなど。「西京人」や「ヤギの目」など新しい形態のコレクティブにも積極的だ。主な個展に「同時に答えろYesとNo!」(2004年、森美術館)、「不完全―パラレルな美術史」(2018年、千葉市美術館)など。第69回芸術選奨文部科学大臣賞受賞。
例えばキリの先っぽが先端であるためには、その後ろに伸びる鋼鉄(スチール)は美術の歴史、あるいは人間の想像力だ。更にその鋼鉄を支える丸く優しい木製の柄は、地球の回転か宇宙のゆらぎだ。それらの力を借りて、キリの先っぽは時代に風穴を開けてゆくのだろう。やがてはキリの先っぽは摩耗してくる。キリの先っぽは常に鋭利でなくてはならない。
担当授業:IMA実技、IMA概論、ドローイング演習
素材と創造性|第10研究室(舞台美術)

原田愛
Ai Harada|准教授|舞台美術家
1981年バージニア(アメリカ)生まれ。東京藝術大学大学院美術研究科先端芸術表現専攻修了。空間を柔らかく変容させることを目指し、舞台美術家として活動している。主な参加作品に「あの出来事」(2019、新国立劇場)、「ミュージカル手紙」(2022、東京建物Brillia Hall)、「スラムドッグ$ミリオネア」(2022、シアタークリエ)、「ライカムで待っとく」(2022、KAAT神奈川芸術劇場)など。
学生時代、より専門的な学びの機会を求めて、私は本学デザイン科を経て大学院では先端芸術表現専攻へ進学しました。様々なアプローチで芸術に関わる教員からの指導、そして学生同士の交流によって、「メディアを横断する」ことの豊かさ、面白さを知りました。私の創作活動は、この時の経験が原点となっています。みなさんと一緒に、創造性について深く思考する場を作りたいと願っています。
担当授業:IMA実技、IMA概論、空間造形演習、空間演出演習
助教

寺田健人
Kento Terada (they/them)|助教|写真作家・美術家
1991年沖縄県生まれ。東京藝術大学大学院美術研究科先端芸術表現専攻修士課程修了。身の回りで起こる出来事をいかにして社会と接続できるかを模索し、写真やパフォーマンスを軸に制作活動を行っている。主な展示会に「態度が〈写真〉になるならば」(2023年、T3 PHOTO FESTIVAL TOKYO 2023)、「想像上の妻と娘にケーキを買って帰る」(2022年、BankART Under35 2022)。第3回PICTH GRANT グランプリ受賞。
担当授業:複合表現演習、プレゼンテーション論
[web-site]